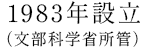受賞者インタビュー
第5回 2024年度 受賞者
【活動内容】
福島県浜通り地方における継続した医療活動
―弱者を取り残さない医療の提供に向けて―
【受賞者】
相馬中央病院 医師/福島県立医科大学 放射線健康管理学講座 博士研究員/医学博士
齋藤宏章氏

「井戸端長屋」住民のコミュニティと健康を支える
福島県相馬市の「井戸端長屋」は、災害復興住宅を発展的に活用した高齢者の共助共同住宅である。約60名のコミュニティの健康を支える訪問医療活動をしているのが、第5回松田妙子賞受賞者の医師・齋藤宏章氏だ。齋藤氏は、能登半島地震の際、井戸端長屋での取り組みが能登半島地震の復興に有用であるとする提言をし、複数の新聞で紹介されたほか、世界的な医学雑誌の一つ『Lancet』にも掲載された。
さまざまな地域の医療特性を経験して
齋藤氏は日本のさまざまな地域の医療現場に触れてきた。1990年福岡県生まれ。両親が医師という環境で育ち、自分も社会の役に立つ仕事につきたいと自然に考えていた。剣道に打ち込んでいたことから警察官になりたい時期もあったが、高校生の時に医師を目指す決意をした。東京への憧れもあり東京大学医学部に進学。研修は地域医療をがんばっているところで学びたいと、北海道の北見赤十字病院へ。その後消化器内科の専門研修を仙台厚生病院で行った。並行して福島県立医大の健康管理学講座にて社会人博士課程を履修し、2022年に博士号を取得した。その年から2拠点勤務で相馬中央病院でも週3日診療し、時には週末も通う。
地域により医療環境も患者さんも違う。北海道では遠方から通院する患者さんをどうサポートできるかを考えた。仙台は先端の医療設備や治療法がある環境。相馬中央病院の患者さんに遠方での治療を勧めるか、地元で最後まで診ていくかの判断を迫られることもある。地域ごとに特徴がある医療の状況と、いろいろな先生から学べたことは、自身の医師としての幅になっているという。
大震災後の弱者への健康的影響
東日本大震災後の被災地域では、住居環境の変化により、生活習慣病の悪化や運動機能の低下が生じていることが知られている。これらの健康的影響は、避難を必要とした人や、一人暮らしで周りの支援を受けにくい人、高齢者などの社会的、身体的な弱者に対してより大きく、悪循環となっていた。また、高齢化もさらに進み、医療のニーズもより高まっている。
齋藤氏は内科医・消化器内科医として消化器がんの診断や治療にあたってきた。その中で、予防的な検診を受けず、がんの発見が遅れてしまう、あるいは発見しても手遅れだったというような事例を多数経験。博士論文のテーマだった、大震災の前後で被災地住民の健康状態がどう変化したか調査したデータもそれを示していた。大腸がんの検診率は、もともと高くはないとはいえ11%あったのが、震災後には2〜3%にまで低下していた。検診自体は行われていたが、精神的にそれどころではなかったり、周囲の支援不足により受診できなかったりしたケースが多かった。そのような経験を通じ、弱者を取り残さないための医療活動の必要性を痛感。大震災の影響を強く受けた福島県浜通りの独居高齢者への医療提供や検診診療への参加、受診勧奨などを通じて、地域医療へ貢献することを目的として活動を始めた。
相馬井戸端長屋への訪問診療の意義
相馬中央病院での業務に加え、震災後に相馬市で設立された高齢者の共助共同住宅「相馬井戸端長屋」に毎月、定期訪問を行い、居住住民の健康管理に貢献している。1回の訪問で、7~8人を診察。熱中症予防のアドバイスから、血圧、体重測定、最近どうですかといった聞き取りなどを行う。以前から井戸端長屋の訪問をしてきた保健師や理学療法士と共同で行うことによって、多面的な支援を提供している。
研修医や地元出身の医学生らにも積極的に参加を促し、彼らの研究調査活動を指導している。それを通して、被災地域の医療の現状と課題を共有し、今後の支援について議論を深め、地域への若手医師定着にも貢献する。
井戸端長屋は災害復興住宅としてつくられたものだが、震災から10数年を経る中で、地元の独居高齢者が入居し、ゆるくつながった半共同生活を送る場として整備されてきた。お互いに見守り共助することで、孤立せず、認知症にもなりにくい。要介護となっても手助けし合いながら生きていけるコミュニティをめざし、それを医療面で支えているのが齋藤氏らの活動である。
2011年当時、相馬地域の高齢化率は26%と当時としては高く、その人たちの医療をどう守っていくかが課題とされた。昨年震災のあった能登は高齢化率が50%を超える地域も多く、齋藤氏は、相馬地域の取り組みが能登にも活かせるとして社会に提言をし、医療面の活動も注目をされている。


自身の成長にも、若手の育成にも生涯学習は必須
高齢社会の健康維持は日本全体の、また医療全体の課題である。今回の受賞を通して、その課題解決につなげるためにも活動を継続し、広く普及していきたいと考える。
社会の役に立ちたくて医師を目指し、日本のいろいろな地域で、いろいろな先生から学ばせてもらっている。医師として、相馬の課題だけでなく、新たな問題がどこで起きても対処できるようになっていきたい。そうなれるよう、自身が成長するために、生涯学習は欠かせないと考える。そもそも活動に関わるきっかけは、第1回松田妙子賞の受賞者である坪倉正治医師が、相馬中央病院で週に1回開いていてくれていた浜通り地域の勉強会だった。勤務後の午後7時~11時くらいで、参加者の取り組みの発表と共有をしていた。共感し、毎週仙台から通った。自分も、地域医療を守るために、若手医師や医療関係者を育成する場を提供していきたいと考えている。坪倉氏の勉強会は形を変え、齋藤氏が、ともに活動する若手らを指導する形で継続している。